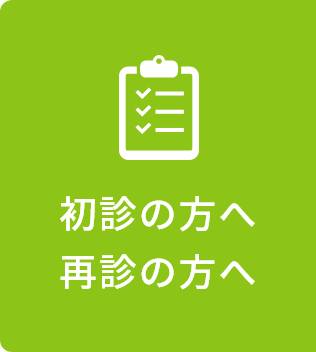人が歩くとは??その9
こんにちは。理学療法士の豊島です
気づけば9月に入りました。
9月に入れど気候は大きく変わらず残暑厳しいですね。
皆様もあともう一息乗り切れば涼しい秋がきますのでもうひと踏ん張りですね(秋もだいぶ短くなりましたが…)
豊島による「人が歩くとは?」の第9回目です。
本日は歩行における年齢の影響をみてみましょう。
皆さん、歳はとりたくないと思いつつも人間が動物である以上、絶対的に避けては通れないのが加齢であり、当然、加齢によって歩行も変化してきます。
では、加齢によって起こる歩行の変化とは具体的にどのようなものでしょうか?
それは「歩くのが遅くなる」…
いやいや、それは目に見えてわかるでしょ?
と言いたくなると思います。
ではでは、より具体的に掘り下げると要因は3つあります
①ストライド長の低下(歩幅の低下)
②歩隔の増大(足幅を広くする)
③ケーデンス(1分間あたりの歩数)の減少傾向
です。
これらはなぜ起こるのでしょうか?
筋力が落ちるから
といわれるとまぁ、それはそうなんですが…
具体的には筋力が落ちてくることで、そのための歩行を安定かつ効率よくするために①~③のことを変化させていると言われています。
ただ一方で、この歩き方は効率的に良くしすぎているが故に、筋力を使うことが少ないため、しっかりと筋肉を使いながら歩くためには、逆に
・歩幅を大きくする
・歩隔を狭くする
・ケーデンスを増加させる
ということにつながります。
加齢そのものは人間の宿命ですので、決して避けて通ることはできませんが、それでも無理のない範囲で以上のことを意識すると、歩行による加齢的変化を遅らせることに少しでも貢献できるかもしれません。
本日の私の投稿は以上です。
以上、豊島でした。
次回もお楽しみに!